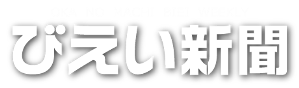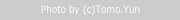インフォメーション
道農政部は10月末までに製糖工場が受け入れた甜菜の糖度は14.9度で、昨年産まで2年間の同時期を下回ったと公表している。
天候にも恵まれ悪い作物はないと言われてきた今年の出来秋。甜菜も収量は平年並みから上回る水準を見込んでいた。しかし最低気温が低いほど糖度が乗る9月になっても、朝晩の気温が下がらず肝心の糖度が低いことが判明した。
美瑛の甜菜を受け入れる日甜士別工場の10月末の平均糖度は14.7度と全道平均より0.4度低く推移している。
糖度が大きく低下した場合、共済制度に加入していれば共済で減収分は一定に補える。ただ、現在の戸別所得補償制度では数量払い交付金単価は、トンあたり6410円であるが、糖度が17.1度を0.1度下回る毎に62円安くなる仕組み。そして13.5度未満となると数量払いの対象とならなくなり、翌年度の営農継続支払い(10㌃当たり2万円)の算定対象にもならない。
美瑛農民連盟の坂田昌則書記長は、甜菜の基準糖度帯の引下げを求めている。
現行糖価調整法の規定では甜菜の交付金対象は13.5度以上となっているため、戸別所得補償もこれに準じて交付される。現行制度の糖度帯の基準糖度は17.1度。全道平均は前年16.1度、前々年は15.3度、今年の予測は15度と基準値を下回っている。この糖度基準を「今年は特別でも良いから、13.5度未満も拾って欲しい」と、基準の見直しを要請している。
収穫作業も終盤に入ったが、受け入れは12月末まで続く。最終的な糖度は未確定だが、戸別所得補償の対象外となれば農家の手取りに大きな影響を及ぼすと危惧されている。
美瑛の今年の甜菜作付面積は1127㌶、栽培戸数は193戸。
MOA光輪花クラブ(中尾隆代表)は7日、町立どんぐり保育園を訪れ、年長組18名の子供たちに生け花体験教室を行った。
「一本の花、一輪の花を楽しんでみたいと思います」と、同クラブのインストラクチャア高橋志津子さんが優しく語りかけた。言葉は話せないけど、命も心もある。1本一本違うけど人間と同じ、心で見てあげるとお花も喜ぶ。部屋に花を飾ると部屋はきれい。また見る人の心まできれいにしてくれるなど、花を生ける楽しみを子供たちに教えた。
まずジュースの空缶に絵柄のついた和紙を貼り、一輪挿しの花瓶を作る。生ける花はバラ、ガーベラ、カーネーションなど多彩。子供たちは順に好きな花を選んでいく。高橋さんが「花をよく見て、きれいだなぁ~という点を見つけてあげて」と花を生ける心を説いた。
同クラブの生け花体験教室は、9月の青葉幼稚園に続いての開催。花のあるくらし、花をきれいだなぁ~と楽しむ心豊かな生活を提案する。
第62回美瑛町文化祭の芸能発表が3日、町民センター美丘ホールで開かれた。会場は雨天にも係わらず朝からほぼ満席となり、身近な出演者に拍手を送った。
芸能発表の出場は17団体、歌や踊りや演奏など日頃の練習成果を遺憾なく発揮した。
スタートは今年も大正琴さつき会のメンバー。「津軽の花」「夫婦坂」などを熱演。舞踏、藤陰可早緋会旭教室、美瑛歌謡会、西岡千佳子バレエスタジオ美瑛教室と続く。午後も民謡・歌謡・ピアノ、ダンスと熱演が続く。
美瑛民謡同志会のステージでは、9月の旭川地区民謡大会で優勝した平田澄子さんの優勝記念卓子掛けも飾られ、民謡「南部俵積唄」が披露された。
また2日から始まっていた作品展は、花は小原流鈴木社中とM・O・A光輪花クラブ。写真は写交会と写真サークルと共に2団体。絵画は美瑛ぱれっとの会、新ロマン派の旭川教育長賞に輝いた花本幸子さんの作品「木漏れ日」も展示され来場者の人気を集めた。主催は美瑛町文化連盟。
美瑛小学校(山崎武光校長)で28日、地域参観授業が行われた。
日曜日の公開授業は先の学芸会に続く家族参加の恒例行事。体育館に全校児童と保護者らが集合し歌声集会。子供達と保護者らが「世界で一つだけの花」を大合唱。
その後体育館で5年生の学年授業「ジャンボ巻きずし造り」が行われ保護者等と5年生が全長30㍍の巻き作りに挑戦した。
5年生はJAびえい青年部の主催する食育事業「あぐりスクール」に参加。同フレッシュミセスの会などの協力を得ながら、米作りを体験してきた。今回使用した米も児童らが植えて刈取ったものと云う。
30㍍の巻き寿司を作るために使用したお米は11升・約25㎏。他に具材として豚壱10㌔、卵110個、キュウリ25本、ほうれん草20袋、紅生姜5袋、美瑛牛乳40本とジャンボに用意した。
巻き寿司造りは15台の長テーブルに海苔300枚を敷き、具財を並べて一斉に寿司を巻く。先生の掛け声にあわせ、千切れないよう慎重な手つきで巻き上げた。
太い巻き寿司を食べ地元産牛乳を飲み、子供たちは「やっぱり、ご飯がおいしいね」と笑顔を見せていた。
美瑛中学校(上用眞一郎校長)吹奏楽部の第30回定期演奏会が20日、美瑛町民センターで開催された。
定期演奏会も回を重ねること30回。その節目の会とあり会場は開演早々にほぼ満席となった。第1回目の演奏会に出場したOB、現在プロとして活躍しているチューバ奏者の国木伸光さんとトランペット奏者の伊藤博樹さんが特別出演。またこの春に卒業した先輩らも一緒に演奏するなど、30年の輝きに花を添えた合同演奏会となった。
中学校の部活動は毎年、卒業と入学を繰り返し、その一年一年が伝統となり思い出となる。今年も32名が夏休みや休日を練習に費やして頑張ってきた。ヘルシーマラソンやいきいきフェスタ、慈光園のふれあい観音祭と、いろいろな機会に町民を楽しませてきた吹奏楽部。今や美瑛中学吹奏学部は、町のイベントには欠かすことの出来ない存在となっている。
今年も6人の3年生がこの演奏会を最後に部活を卒業する。本当に「3年間ありがとうございました」