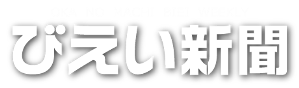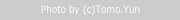インフォメーション
美瑛の雪原に巨大な雪上絵が現れた。写真撮影を待ちかねたように小雪が舞い、雪上絵のはかなさを見せ付けた。
第5回「美瑛の雪上絵フェスティバル」が23日、美瑛町水沢ファームレストラン千代田の丘陵で行われた。
今年の雪上絵も「とんぼの未来・北の里づくり」のロゴマークと、十勝岳の山並みに囲まれた青い池を鮮やかな色調で描いた。
真っ白な雪原にヨコ100㍍×タテ90㍍の巨大な雪上絵を描こうと、要所ごとにGPSでポイント付けて準備した。当日は旗の色と同じ色の絵の具を撒いて行くこと。使うのは環境に優しい卵の殻や融雪材の粉末絵の具。
作業を担うのは町内のボランティア約100名。美瑛の雪上絵フェスティバル実行委(薦田哲雄会長)の活動に賛同する有志が集った。
美瑛町報徳社(浦島規生社長)は第24回実践農業講座「TPP講演会」を19日、JAびえい大ホールで開いた。この講演は美瑛町婦人団体連絡協議会(荒井妙子会長)の美瑛町女性のつどいを兼ねた。
TPP講座は東京大学大学院の鈴木宣弘教授を迎え、「TPPと私たちのくらし」をテーマに講演した。
22日に予定されている日米首脳会議でTPPが取り上げられる可能性は大きい。自公政権は「TPP反対」を公約し、昨年末の総選挙に勝った。しかし「聖域なき関税撤廃」でなければ良いと、官邸主導での交渉参加の決定をちらつかせている。
鈴木教授は、現状は「情報収集のための関係国との事前協議」の段階ではない。米国の要求する「入場料」(自動車、保険、BSE)の詰が進んでいる。米国がそれらを払ったと認めたときが、実質的な日本の「参加承認」。まだ米国が認めていないので、日本の決意表明も見送られてきた。
決して国民の懸念を反映し、参加表明が見送りされているわけではない。また、「参議院選挙まで参加表明しない」と言うのも国民をばかにした話だ。選挙後すぐに公約を覆してよいのか、そういう気配が感じられたら、断固とした対応をとらざるを得ないと力説した。
大会を盛上げたのは、美瑛出身の青嶋ひかるさん。小学生から同大会に出場しその活躍は広く知られている。交歓式では招待選手として夏目円選手と共にステージに登場。競技では宮様コースに出場し寬仁親王妃牌を獲得した。
ゴール直後には「レースは厳しかったが、楽しかったです」と嬉しそう。卒業後は東京の大学へ進学する。推薦ではなく「地力ですよ」と笑顔で応えた。
「第36回宮様国際スキーマラソン」が17日、美瑛の特設コースで開かれた。
昨年6月亡くなった寬仁親王殿下の追悼大会。昭和53年「第1回北海道歩くスキー交歓会」からの長年に亘るご支援、ご指導を賜り、大会も「寬仁親王記念」と冠することとなった。大会には寬仁親王の長女、彬子女王殿下が交歓会や表彰式に出席した。
快晴に恵まれたビルケの森の午前9時、美瑛の丘を疾走する宮様コースがスタートした。快晴ほぼ無風、気温はマイナス21度。宮様コースのエントリーは268名。先頭は招待選手の青嶋ひかる選手。
また、同時刻に歩くスキーコースがビーフイン千代田をスタート、エントリーは219名。招待選手の夏目円選手も子ども達と一緒にスタート。最後に20㌔コースの409名がビルケの森をスタートした。
水沢平誠会は水沢行政区会館で6日、平成24年度畑作物共励会を開き、上位成績者を表彰した。
「秋まき小麦の部」と「春まき小麦の部」で第一位の成績を上げたのは栢木敏夫さん(水沢)。秋まき小麦(きたほなみ)で10㌃当たり808㎏、春まき小麦(春よ恋)で566㎏と共に高い収量を上げた。また、「てん菜の部」では渡辺武志さん(水沢新生)が糖分16.2%、糖量で10㌃当たり1351㎏と高い実績を上げた。特に厳しかった今年のてん菜糖度の中で、16.2%は立派と称えられた。水沢平成会は町内でも高い生産性を誇る。その中の最優秀者として、大島一之会長から表彰状が手渡された。