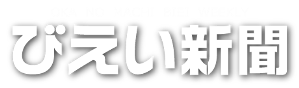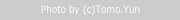インフォメーション
更新に手が回らず、失礼しております。
新聞は、毎週土曜日発行で続けております。
最近の内容は、こんな感じで…。
9月26日号 №1774
●お家騒動の引き金?理念にそぐわないメッセージに待った。
町社協に自民党美瑛支部が質問状
●第7回町議会定例会 補正予算で垣間見えた町民不在のまちづくり
●望岳台旧レストハウス解体完了。防災シェルター建設は来年度に
●1千万円の「おねだり」の価値はいかに。冬の観光振興で高級ライトを追加購入
●第6回丘のまちびえいセンチュリーライド開催
●美馬牛中で文化祭/美沢小にサイエンスカー訪問/美瑛小で人権の花運動
●皆空窯で年に一度の窯焚き/美瑛ポテトの丘でゴミ広いツアー
●忠別地区の元住民らが小公園整備/マイナンバー対策研修
その他もろもろ、この号は拡大版8ページの盛りだくさんの内容でした。
「びえい新聞」は、3月末で休刊を余儀なくされていましたが、地域の皆様から復刊を望む声も多く、新しい編集者を迎え、6月7日より再び発行をスタートさせています。
小さなまちの小さな新聞ですが、より充実した紙面づくりのもとで、地域のための地域の情報を伝えていきます。
ホームページでの美瑛町の情報発信も行っていきますので、よろしくお願い致します。
びえい新聞 興梠
第39回すずらん大学卒業式並びに修了式が6日、町民センター3階で開かれた。
拍手で待ち受ける会場に真赤なリボンを胸に12名の卒業生、黒いマントに角帽姿の博士課程修了生11名が胸を張って入場する。 歌詞をかみ締め大声で歌う「美瑛、美瑛、美瑛すずらん大学校~」の校歌斉唱。
千葉茂美学長から卒業証書を手渡され感無量の面持ちで胸を張る卒業生ら。「学習に終わりはない、卒業式は生涯学び続けていくとの決意の場」と千葉学長が式辞。在校生を代表し寺林宏一さんが送辞を述べ、武田章司さんが卒業生を代表して「卒業したことに誇りを持ち、感動を財産として、町の発展に力を尽くす」と力強く答辞を述べた。
美瑛町農民連盟(小野寺雅芳執行委員長)は1日、第66回定期総会を農協3階大ホールで開催した。
小野寺委員長は開会の挨拶で「昨年はTPP反対に費やされた1年だったが、未だに予断を許さない」と警戒と監視を呼びかけた。また「昨年暮れに大きな農政改革が発表された。しかし我々としては真の農政改革を目指していく。そのために生産現場の代表を国会に送り込むことが必要だ」と訴えた。
来賓は浜田町長、齋藤議長、北口雄幸道議、大西昭男組合長、佐々木隆博前衆議院議員、それぞれ反TPPを話題において祝辞を述べた。
総会の冒頭、TPP交渉即時脱会「真の農政改革」実現を求める特別決議を採択。 「国民の命と暮らし、国家主権さえ脅かす異常な協定、TPPからの即時撤退」「産業競争力会議や規制改革会議主導による農業改革推進に断固抗議」「北海道農業・農村が果たしている食料の安定供給や多面的機能の発揮、農村社会の活性化を図る、真の農政改革の実現」を全員の拍手で承認した。
久しぶりの快晴、青い空、見渡す限り真っ白な雪。水沢春日台の丘陵に22日、色鮮やかな雪上絵が登場した。
今年の絵柄は、札幌市立大学の学生らがデザインした。美瑛の丘に虹が掛かり、美瑛の丘陵に3本の木、空には虹が。そして中央にトンボ「とんぼの未来・北の里づくり」のキャッチコピーが飛んだ。
雪上絵は横110㍍、縦90㍍と巨大、全地球測位システム(GPS)を使って下書きし卵の殻と黒い融雪剤を使って書き上げた。
冬の美瑛で大勢の人が交流する。美瑛らしく真っ白な雪原に大きな絵を描こう、そんな思いから始まった美瑛の雪上絵は、「トンボやホタルが生息する水辺や環境を守り育てたい」と水沢環境保全組合が活動の一環に加えたもの。